![]()
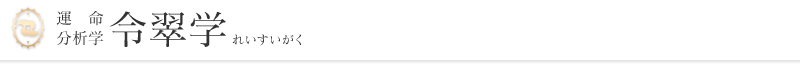
 2014年2月12日
2014年2月12日鑑定士:碧令翠(027) 女性の時代を観る…「科学で分析する母性とは」…Part1 悩み相談で最も多い「人間関係のストレス」…は、自分を知る事が第1と常々提唱してきましたが、その「自分のアイデンティティ」の構築に最も関与する「母親」について今回は分析をしてみます。 社会が成熟するに従って、うつ・依存症・摂食障害・自傷行為・引きこもり・虐待・無気力など、文明病と言われる様な相談が後を絶ちません。 …以前生物としての「男女の違い」を女性の時代の受難として、お伝えしましたが、女性なら誰でも生まれながらに、当然の様に獲得された能力と思い込まれている、能力「母性本能」…について考えてみましょう。 <何故?哺乳類か!> ◎生物学的究極のシステム…(愛着システム) 「腹を痛めて産む」そこから始まる関係の真実は、陣痛の真っ只中で、大量に分泌されるホルモン「オキシトシン」が関係している。 このホルモンは苦痛を歓びに変え、不安を鎮め安らぎを与えます。 このホルモンの不足は将来の「対人関係」に大きく関わり、ネガティブ思考の支配を受ける要因となります。 母子の絆はその後授乳を通してさらに深まり、抱っこや愛撫などのスキンシップが、それをさらに、持続的にして行きます。 オキシトシンを受ける受容体の数もこの時期に確定します。 つまり幼い頃にどれ位愛情深く世話を受けたか?…否かが将来を決めるのです。 大切に育てられた人ほどオキシトシンの働きが良いので、ストレスに強く人を愛することが容易になる訳です。 ◎基本的安心感は、ゼロ才〜2才(記憶になくても体験で形作る) 出産後寝る間も食も全て「子供に没頭する日々」…が母性と言う「自分育て」の原点になるわけです。 残念ながら、血を引くだけで、母子愛は産まれないのです。 全ての優先事項が、ある時期まで「乳児」…に注がれて初めて「親」と「子」になるのです。 この時期に母親との愛着が出来た子供は「幸せホルモン→セロトニン」の受容体が多くでき、将来不安などのコントロールが上手に出来る様になります。 人格形成の基礎はまさに、出産の痛みと共にスタートを切り、子育てが親も育てるチャンスになるのです。 特に日本人やアジアの人々は「不安を強く抱く遺伝子」を多くの人が持ち、日本人の2/3が該当すると言われています。 日本が先進国と言われる以前の「子育て」を見直す事が、これからのトレンドであり、真の「英才教育」…と言われる日が間も無く来るのです。 次回を乞うご期!! |